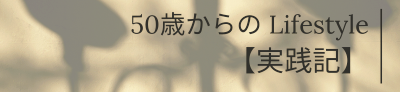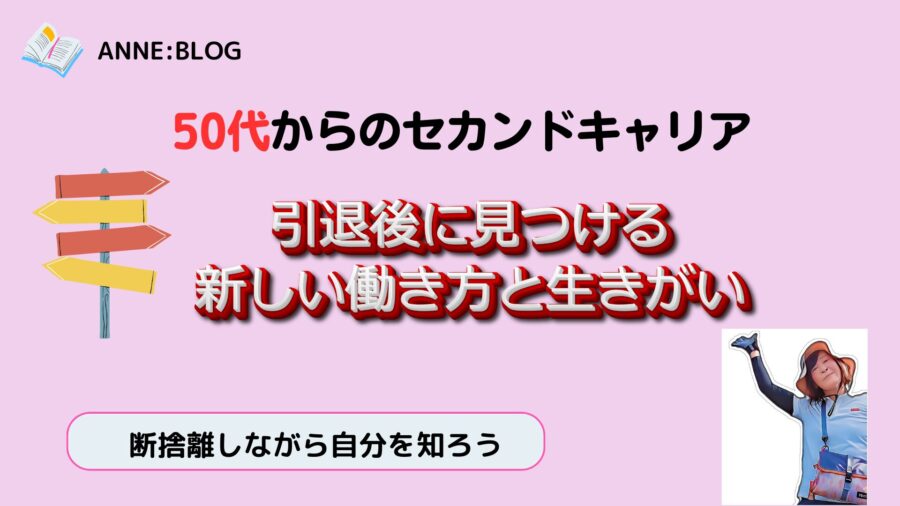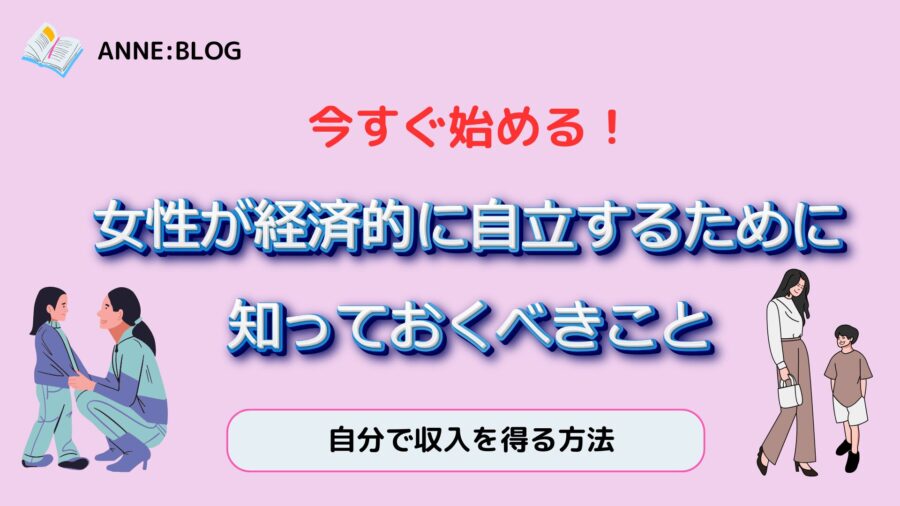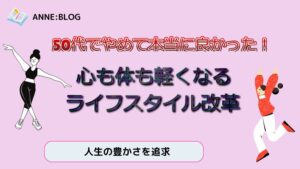
この記事は、50代でやめることで心も体も軽くなるライフスタイル改革について解説しています。
50代になると、気力や体力がいっきに落ちてきたように感じませんか?
- 寝ても仕事の疲れがとれなかったり
- 休日は家でゴロゴロすることが多くなったり
- 考え事が増えたり
このような生活を送っている50代、実は多いんですよね。
そのいっぽうで、現状を変えたいと思っている人も多いのです。
すでに何かをやめてみて、変わったことはありますか?
まだ、何をやめていいのか分からない人もいるのではないでしょうか?
最初は変わることよりも、無駄なことをしていないかチェックしてみるのも1つの方法です。
無駄をやめることで、変わるきっかけに繋がることが多いのです。
 杏
杏 この記事で分かることは、
・50代でやめてよかったことは?
・やめたことがもたらしたメリットとは?
・やめるべき習慣の見つけ方とライフスタイルの向上とは?
この記事を読むことで、「やめて良かった」と、実感できる習慣や考え方の変化を理解することができます。
50代でやめて良かったこと一覧

最初に、50代でやめて良かったことについてお伝えしていきます。
- 仕事での悩みはないか?
- 体調面で悩んでいることはないか?
- 人との関わりで悩むことはないか?
上記は、生活の上で誰もが悩まされる課題になります。
では、詳しくみていきましょう。
過度の仕事へのプレッシャー
50代は、子育てに一段落する時期になるのではないでしょうか。
しかし、その一方で親の介護が始まることも少なくありません。
それ以外にも、自分の時間を有効に使うために仕事と生活のバランスはとても重要になってきます。
例えば、
- 残業が当たり前の仕事をしている
- 休日が少ない仕事をしている
このように、仕事が中心になっている生活を送っているといったことありませんか?
無理な労働型の仕事への執着をやめることで、時間に余裕ができ思考が働いてきます。
思考が働くことで、時間に余裕が持てる仕事にチェンジする視野も広がってきます。
 杏
杏 時間に余裕が有る無しで、メンタルにも影響がでやすいと言われています。
身体と心のバランスを考え、仕事を選択するとよいのかもしれません
不健康な食生活や運動不足
時間に追われる生活を続けていると、食生活の乱れがおこりやすくなります。
例えば、
- 簡単なカップラーメンで済ませたり
- レンジで温めるだけの単品料理だったり
- ストレスから甘いものを取り過ぎたり
このようにな食が、習慣化していることってありませんか?
簡素な食事を習慣化することで、健康に及ぼすリスクが高くなります。
継続していれば、最終的に自分に返ってくるので異変が起き辛くなることもあります。
悪い習慣を見直し、良い食生活と適度な運動を取り入れることで身体も気持ちも軽くなってきます。
慣れた習慣化をやめることで、自分自身の身体が変化していく様子が実感できるでしょう。
 杏
杏 私は食生活と運動を改善して15年になりますが、体重は7kg減になりました。結果的に身体が軽くなり体力がついたのです。
自分の身体は自分でコントロールすることで快適度が全く変わってくると思ってます
不要な人間関係の整理
ストレスを感じる人の付き合いや、不要だと思う人の関係を整理していきます。
例えば、
- ストレスを感じつつも無理にお付き合いを継続していたり
- 価値観のズレから合わなくなってきたり
自分にとって、不快に感じる人っていませんか?
50代は、自分にとって居心地の良さを基準に人間関係を見直すことも大切です。
人との関係は良い時もありますが、ストレスを感じやすいのは人間関係とも言われています。
煩わしさを感じながら関係を維持しても、自分のためになりませんよね?
必要な人だけと大切な関係を築けたらメリットも大きいはずです。
自分にとって必要な人はどのような人でしょう?
- 知識が多く学ぶことが多い人
- ほどよい距離感で接してくれる
- 行動力がある人
このように自分にとって、プラスになる人ではないでしょうか?
ポジティブな人の影響力は大きく、生活に変化をもたらしてくれる可能性があります。
 杏
杏 類は友呼ぶといった言葉がありますが、今の人間関係は自分にとってどんな影響を与えているのか?を、考えてみると必要と不必要に分かれていくのではないでしょうか
やめたことで得られるメリット

次に、やめたことで得られるメリットについてお伝えしていきます。
時間の有効活用
仕事と生活のバランスを考えることで、時間の有効活用ができるようになります。
人が幸福を感じる時って、どのような状況かご存じでしょうか?
それは、お金と時間のバランスです。
どんなにお金を稼いでも、寝る時間も生き抜く時間も無かったら、幸福を感じないと思うんですよね。
なぜなら、お金を稼いでも活用する時間がなければ意味がないからです。
お金は自己投資することで、幸福度が上がってくると言われてます。
例えば、
- 海外旅行へ行くために英会話を習得する
- 体力強化するためにパーソナルジムに通う
- 起業するためにノウハウを学ぶ
上記は、目的を達成するための時間と投資になります。
体験をすることで、自己肯定感が高まり前向きに進むことができるのです。
 杏
杏 時間があれば自分を見つめ直すこともできますし、仕事を変えたり何かに挑戦してみようと考えることもできますよね
50代からのセカンドキャリア、引退後に見つける新しい働き方と生きがいについて解説しています。この記事で分かることは、・50代になったらやめるべきこと・50代からセカンドキャリアを始める理由・セカンドキャリア見つけるためのステップ・50代からの成功事例
健康面での改善
食生活や運動を改善することで、体調が整ってきます。
50代は、変化も大きい時期でもあるので意識しておくことが大事ではないでしょうか。
例えば、
- 血圧が規定値に改善されたり
- だるさが取れたり
- 足腰の痛みが軽減されたり
- 肌の調子が良くなったり
それ以外にも、身体が循環することで気持ちの面でも軽やかになってきます。
心身共にバランスがとれることで、質の良い睡眠をとることもできます。
 杏
杏 基礎代謝の低下からくる肥満やホルモンの崩れなどは、サプリメントよりも食事や運動で改善されることもあるのです。
私自身、食事と運動を見直したことで更年期の不調を感じず生活を送ることができています
心の軽さと幸福感
人間関係を整理することで、自分の時間を楽しむことができます。
人に依存しないことで、快適なライフスタイルを自分で作っていくことができます。
1人の行動が増えることで、今まで見えなかった風景や注目すべき目線が変わってくることもあります。
例えば、
- 1人でのランチでは、食材やお店の雰囲気を味わったり
- 散歩の時は、風景や周りの人を観察できたり
- 旅先では、自由にプランを練ることができたり
- 趣味に時間を費やすことができたり
今まで気づかなかった発見があることが、ほとんどです。
 杏
杏 人に合わせて行動すると、会話や気遣いから場所や風景などの感覚が薄れてしまうことがあるのです。
例えば、場所までの道のりや、その場の雰囲気をあまり覚えてないことってあるのではないでしょうか?
年齢を重ねると、少しずつ人間関係の距離感が変化してきませんか?人との関わり方がめんどうと感じるのが多くなったけど、単に歳のせいなんだろうか?仕事や、生活の中で普通に会話はできているのに親密な関係にはちょっと距離を置きたい50代の女性の距離感の悩みを詳しく見ていきましょう。
50代がこれからやるべき習慣の見つけ方とライフスタイルの向上

最後に、これからやめるべき習慣の見つけ方とライフスタイルの向上についてお伝えしていきます。
50代は、少しでも居心地が良い生活を送ることを意識することが大事ではないでしょうか。
私なりの考えになりますが、頑張る時期は終わったと思っています。
もし、この先も今と同じ生活パターンを続けていくことに有意義を感じるでしょうか?
「この先」は、無限ではありません。
そして、この先よりも「今が1番若い」と、いった意識づけも必要ではないかと思っています。
では、詳しくみていきましょう。
自己分析をする
自己分析は、自分自身に質問を問いかけてみましょう。
- 仕事に追われていないか?
例えば、そこまでやる必要があるのか?違う仕事にチェンジしてもいいのでは?無理して働いていないか?
- 体調に異変を感じていないか?
ストレスで甘いものを食べすぎていないか?コンビニ弁当や冷凍食品を食べていないか?面倒で運動を全くしていない?
- 今の自分に必要なことは?
人間関係で悩んでいないか?旅行に行けているか?趣味を持っているか?優先順位の区別をつけられているか?
現状の生活習慣を振り返り、ベストな自分でいられているかを確認してみましょう。
自分にとって不要なものをやめることは、心身と健康に大きな影響に繋がってくるのです。
小さな変化から始める
生活習慣を見直し、変えることは重要なポイントになります。
大きな目標を立てることはモチベーションになりますが、急に生活を変えるのは大きな負荷がかかります。
そのため、挫折しやすくなるので小さなことから始めることが大切です。
例えば、
- 将来を考え副業で収入を得られるようにする
- 週2回1時間程度のウォーキング、またはジムに通う
- 1人でプランを立て日帰り旅行をしてみる
小さな変化は、ハードルも高くないので「始めてみよう」という気持ちだけで行動できます。
行動することで成功体験が積み上がるので、後にそれが大きな変化になってくるのです。
ライフスタイルの質を高める
ライフスタイルの質を高めることを意識することが大事です。
過去の自分の成功体験や失敗体験から、今の自分そしてこれから先の自分の「こうでありたいライフスタイル」をイメージしてみましょう。
- 時間に追われない生活
- 趣味や旅行に行ける生活
- 自分の意志で行動できる生活
- 物や人に依存しない生活
- 健康を意識した食生活
このように、思うことを書き上げることでやめるべきことが明確になり行動に移すことができます。
頭の中で思っているだけではなかなか動かないのが人です。
なぜなら、人は変化を嫌う動物だからです。
特に日本人は、人と違うことをしたがらない傾向が強いのです。
ただ、自分の人生に人は関係するのでしょうか?
人に左右されてた人生になってしまうのではないでしょうか?
すべては自分のために変わる、やめることなんですよね。
まとめ
今回は、50代でやめることで心も体も軽くなるライフスタイル改革について解説しました。
まとめると、
- 50代でやめて良かったことは、無理な残業や過度の仕事、不健康な食生活と運動不足、不要な人間関係の整理
- やめたことで得られるメリットは、仕事と生活のバランスを考えることで、時間の有効活用ができるようになる。
食生活や運動を改善することで、体調が整ってくる
人間関係を整理することで、自分の時間を楽しむことができる
- やめるべき習慣の見つけ方とライフスタイルの向上は、現状の生活習慣を振り返り、ベストな自分でいられているかを確認する。
急に生活を変えるのは大きな負荷がかかるので小さな変化から始める
過去の自分の成功体験や失敗体験から、今の自分そしてこれから先の自分の、こうありたいライフスタイルをイメージし行動する
いかがだったでしょうか。
私は50代を迎え自分の生き方を考え始めました。
- 仕事とお金
- 健康
- 人間関係
やはり、この3つです。
行動したことは、副業を始めたことで本業以外に収入源を得ることができました。
また、健康を意識しジムに通うようになり同時進行で食事の見直しをし、その結果、身体が軽くなり体力もついてきました。
高価な化粧品は使っていませんが、代謝が良くなり肌が綺麗になったことも実感しています。
そして、価値観が合わない友達とは距離を置くようにしたのです。
付き合いが悪いと思われているかもしれませんが、自分の人生ですから時間は有効に使いたいですよね。
この記事が、新しい人生のステージに備えるため、不要な習慣や行動を捨てることで自分を成長させるための参考になれば幸いです。
 杏
杏 ブログに関して気になること、またブログ以外でも質問が
ございましたら下記フォームをご利用ください